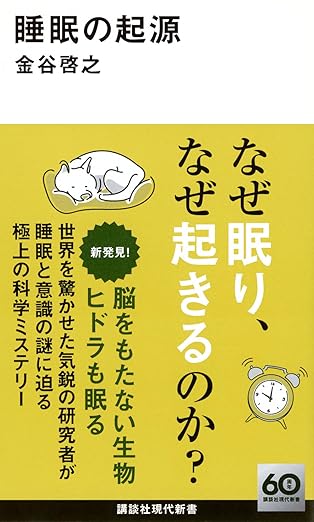
『睡眠の起源』 金谷 啓之 (著)
私たち人間や犬猫といった生き物たちは、当たり前のように睡眠という状態を取ります。
さらに言うなら、寝ないと健康を害を及ぼすことさえあるため、睡眠は生きていくうえで必ず必要なことでもあります。
でも、なんで寝る必要があるのだろう。
本書の中でも、生き物が必ず寝ることへの疑問として、何億年もかけて、不必要なものを削って進化してきた私たちが、なぜ『睡眠』という無防備な状態になることをなくすことがなかったのか。
という話がありました。
確かに、自然環境の中で生きていくことを考えるならば、睡眠状態のようなとても無防備な状態は、なるべく避けた方がいいと思う所です。
寝ている間に、他の生き物の餌食となってしまったり、攻撃されたりと、睡眠状態というのは、ある意味とても危険な状態です。
寝ないでいられれば、もっと活動的に人生という時間を有意義に生きることが出来るのではないか、と思うのも当然なのかもしれません。
人生の三分の一は寝ている状態
私たち人間は、人生の約三分の一を寝て過ごすことになります。
しかし、そもそも『寝ている』とはどういう状態なのかという疑問が湧いてきます。
目をつむっている時?、意識がない時?、夢を見ている時?、動きがほどんどない時?、睡眠という概念は、意外と私たちが思っている以上に難しい話なのかもしれない。
レム睡眠やノンレム睡眠、睡眠といっても複数の睡眠状態があることもわかっている。
また、最近ではスマートウォッチなどを使って睡眠状態を調べることができるようにもなってきたけれど、どのタイミングで睡眠状態に入ったとするのか、スマートウォッチの計測だけで、はっきりそれとわかるだけの変化があるものなのだろうかと思ったりもする。
睡眠の状態を脳波で計測する話は、よく聞くことがある。レム睡眠やノンレム睡眠などは、脳波を計測すると、その状態にあることが分かると言います。
また、レム睡眠中には、夢を見ることがあるという話も有名です。
睡眠という状態は、脳を休ませている状態だという話もよく聞きます。私たちは睡眠中に情報や記憶などを整理しているという話だったように思います。
つまりは、生き物というのは、脳があるから睡眠をとる必要があるのだと思っていましたが、本書によると、実はそうではないという事を教えてくれています。
なんと、脳という臓器のない生物であっても、睡眠はとっているという話です。
この本の著者の研究していた『ヒドラ』という生き物には、脳という臓器がないらしいのですが、観察していると、まるで寝ているかのように動きが少なくなることがあるのだそうです。
寝ているかどうかの判断は、脳という臓器の活動状態で決まると言っていいのだろうか?
『睡眠』って一体何なんだろう?
本書は、そんな睡眠の不思議についての話を、著者のこれまでの研究人生と共に、いろいろと語っています。
そして最後に、これまでの長い科学の歴史のなかでも、いまだに答えを得られていない『意識とは何か』という最大の謎の解明に、睡眠という現象を理解することでつながっていくのではないか、というロマンを感じさせる話へとなっていきます。